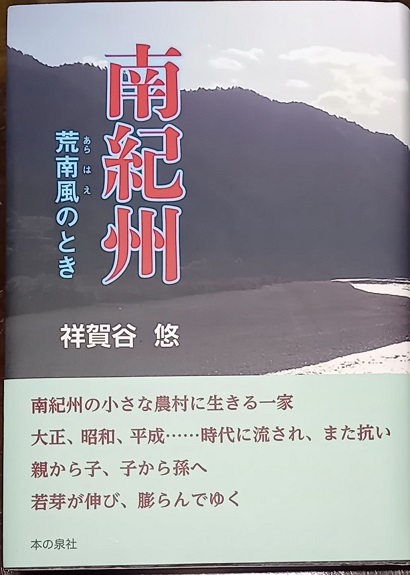大正5年12月12日。夏目漱石の葬儀に森鴎外が姿を見せたとき、受付をしていたのが江口渙と芥川龍之介だった。以下は、江口渙の回想だ。
森鴎外が姿をみせた。鴎外は絵かきがするように上のへりをまるく折ったツバの広い黒のソフトに、黒の二重まわしを着ている。そして胸を張った巖丈そうな足どりで受付めがけて颯爽と近づいて来た。われわれの前まで来て立ちどまると、帽子をとってみんなの顔を見わたし、礼儀正しく頭を下げた。精力家らしい赤味をおびたつやつやした顔。強い光を放った鋭い眼。ややとがった鼻。きゅっとかたく結んだ口もと。殊に、気持ちのいいほど広くみえる額のへんには、いかにも豊かな知性と創造力とが湧きあふれてやまない感じがはっきり出ている。
鴎外は大型の名刺をわたしの前に置いた。「森林太郎」とあるだけで、ほかに何もない。わたしは名刺をそっと芥川の前に置きかえた。芥川の眼が名刺と鴎外の顔とを見くらべた。と思った瞬間、鋭い緊張感が顔一面にあふれ、その瞳は異常な光を放って鴎外の顔を見つめた。われわれも丁重な挨拶を返した。だが、それっきりわたしも芥川も暫くはものを言わなかった。そして鴎外の後姿がやや遠のいたとき、芥川がはじめて息をはずませて話しかけた。
「あれが森さんかよ」
「そうだよ、森さんだよ。君はいままで知らなかったのかい」
「うん、初めてだよ。いい顔をしてるなあ、実にいい顔だな」
芥川は指を広げて長い髪の毛をぐっとかき上げると感嘆おくあたわずという風に、何度も「あれが森さんかよ、いい顔だなあ」と同じ言葉をくり返した。